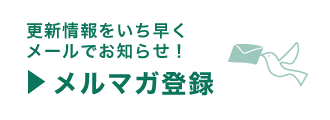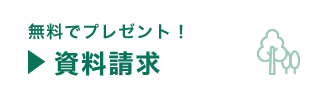収穫後の稲わらは、かつて野焼きされることが多くありましたが、EMが国内で広がり始めた1980年代の中期からEMを活用することで焼かずに分解できるようになり、その後、多くの収穫残渣の早期分解法として広がっています。
最近では、分解したい有機物にEM整流炭や塩を0.1~0.5%を添加し、EMを10a当たり50~100Lくらい散布すると、たちまちにして肥沃な土壌にすることも可能となっています。
40年ほど前にタイ国のテレビインタビューで、野焼き問題はEMにより完全に解決できることを説明し、同国サラブリの自然農法センターが所有する200haの土地でキングプロジェクトとして実施しました。この成果は各地に着々と広がり、CO2問題の認識が高まるとともに、野焼きは極端に少なくなっています。

タイ国の隣国であるミャンマーもEMが導入され30年以上になりますが、EM活用の多様化が着々との成果をあらわし、社会化しています。
以下に紹介するのは、2024年9月イギリスの非営利投資ファンドであるGIFが野焼きの防止と収穫残渣の高度なリサイクルを目標に、ミャンマーに投資を行ったニュースです。このプロジェクトは公的機関が実施するものであり、今後の展開が楽しみです。

Global Innovation Fund(GIF)、ミャンマーに初の投資
2024年09月09日【以下、DeepL自動翻訳抜粋要約】GIFは、ミャンマーで農民が収穫後の稲株を除去するための実用的なソリューションに50万ドルの助成金を提供したことを発表します。
Proximity社アプローチは、作物残渣を効果的にバイオ分解機の技術を促進し、土壌の健全性と作物収量を向上させます。 この方法によって、伝統的な露地焼畑の必要性が完全になくなり、年間炭素排出が削減される。
高品質な土壌は、食糧供給を確保し、収入増加への道を提供する。しかし、広く行われている野焼きは、土壌の質を低下させ、大気汚染を通じて人間の健康にも悪影響を与えている。
世界的に見ても、稲作農家は収穫後の残渣を取り除くために田畑を焼くが、ミャンマーでは毎年30万人以上の農家が野焼きをしている。 零細農家にとって、焼畑は最も一般的で便利な方法で、次作に向けて土地を開墾する唯一の選択肢である。
Proximity社は「無焼畑稲作」と呼ばれる解決策を提供。これは、田畑の刈り株を短時間で分解し、野焼きの必要性をなくすものである。 この方法はEM(Effective Microorganisms)と呼ばれる微生物製剤またはバイオ分解剤と、窒素肥料の2つの資材を組み合わせて使用する。 農家は、この液体製剤を散布し、2週間以内に株立ちを分解させる。 この農法は、必要な化学物質の投入量を減らし、土壌の健全性を回復させることで再生農業への移行を促進し、収量の増加、病害虫の発生減少による作物の損失減少、大気環境の改善につながる。
GIFの助成金は、Proximity社がミャンマーの46,000の稲作農家にこの方法を提供し、有効性に関するエビデンスを構築し、長期的に農家に優しい実用的な解決策を他の稲作国でもこの革新的技術を再現できるよう支援する。
(元記事:https://www.globalinnovation.fund/news/our-innovations/gif-supports-innovation-to-improve-climate-resilience-of-rice-farmers)
その次にインドの状況についてです。EMによる有機物や収穫残渣の有効活用法や輪作への応用の記事が出ていますが、EMに対する理解度がかなり高まっている内容となっています。インドは国の研究機関もEMを積極的に取り上げ、農業はもとより、環境問題の根本的な解決に広く使われるようになっています。
以下にその事例を紹介します。

有機農業のイノベーション 輪作と残渣管理を変えるEM
2024年12月15日 by Shivam Singh【以下、DeepL自動翻訳抜粋要約】 有機農業は、環境にやさしい実践と長期的な土壌の健全性を重視し、持続可能性の道標となっている。 この領域を再構築する重要な技術革新のひとつに、有益なバクテリア、菌類、酵母のブレンドである有用微生物群(EMs)の利用がある。これら微生物は、輪作や残渣管理において、土壌肥沃度を高め、作物の生産性を向上させる自然な方法を提供し、変革をもたらすことが証明されている。
有用微生物群(EMs)
有用微生物群(Effective Microorganisms:EMs)は、単一の種ではなく土壌の健全性を向上させるために働く自然界に存在する微生物の複合体である。 微生物のバランスを回復し、栄養の利用可能性を高め、有機物の分解を促進する。 化学物質投入を減らし、生態系の調和を高める有機農業の原則に合致しているため、有機農業におけるEMの役割は特に重要である。 EMを農法に取り入れ、土壌生態系を豊かにし、害虫対策や栄養分の枯渇といった課題に対してより強くなることができる。
EMが輪作を強化する方法
輪作は土壌の肥沃度を維持し、害虫の発生を抑え、同じ土地で異なる作物を連続して栽培することができる。 EMはこのプロセスをより効率的で持続可能なものにすることができる。第一に、EMは作物有機残渣を分解することで、養分のリサイクルを促進する。 この分解によって、窒素、リン、カリウムなど養分が放出され、次の作物に容易に利用できるようになる。
有用微生物(EM)による残渣管理
ワラ、株、葉などの残渣を管理せずに放置すると、害虫が発生したり、栽培効率が低下したり、焼却による汚染などの環境問題につながったりする。EMは、残渣管理に環境に優しい代替手段を提供する。EMを作物残渣に散布すると、分解プロセスが促進される。 EMは、リグニンやセルロースなどを単純な化合物に分解し、有機物で土壌を豊かにする。このプロセスは、次作のために畑をきれいにするだけでなく、大気汚染や温室効果ガス排出の原因となる残渣焼却のような有害な慣行を不要にする。EM処理した残渣は、優れた堆肥源になる。 農家は、この栄養豊富な資材を天然肥料として使用することができ、化学合成品への依存を減らすことができる。 このアプローチは、自立した有機農業システムの原則に沿ったものである。
有機農業におけるEMの利点
- 有用微生物群には、有機農業において貴重なツールとなる数々の利点がある:
- 土壌の肥沃度を高める: EMは土壌状態、栄養分、微生物多様性を改善し、植物の生育に理想的な環境を作る。
- 持続可能な残渣管理: EMは、作物残渣を貴重な有機物に変え、環境への害を減らし、土壌を豊かにする。
- 病害虫防除の改善: EMは有益な微生物を促進することで、有害な病原菌を自然に抑制する。
- 化学物質への依存度の低減: EMの栄養循環と病害抑制能力は、化学合成肥料や農薬の必要性を最小限に抑える。
- 気候の回復力 EMは土壌の保湿を助け、異常気象の影響を緩和し、干ばつや洪水による作物の生育をサポートする。
EM技術導入の課題
多くの利点があるが、有機農業におけるEMの導入には課題がないわけではない。 農家は、高品質のEM製品を入手することが困難であったり、EMを効果的に使用するための技術的知識が不足していたりする。さらに、極端な高温や不適切な使用は効果を損なう可能性があるため、EMの保管や取り扱いには注意が必要である。 こうした課題を克服するため、農業団体や政府は、研修プログラムや意識向上キャンペーンに投資しなければならない。また、EM製品に補助金を支給したり、コミュニティでの堆肥化の取り組みを奨励したりすることも、小規模農家がこの技術をより利用しやすくするのに役立つ。 有機農法、特に輪作と残渣管理への有用微生物の統合は、持続可能な農業システムの構築を可能とする。
土壌の健全性を向上させ、養分のリサイクルを強化し、環境への影響を軽減することで、EMは環境に優しく、強靭な未来への道を開く。 農家や農業団体にとって、EM技術の導入は単なる選択肢ではなく、気候変動や食糧需要の増加に直面する中で必要不可欠なものである。継続的な革新と支援により、EMは有機農業に革命をもたらし、長期的な農業の持続可能性を確保することができる。 土壌を育て、環境を保護し、農業の未来を守るために、この微生物革命を受け入れよう。
(元記事:https://www.indiafarm.org/agriculture/organic-farming/organic-farming-innovations/)