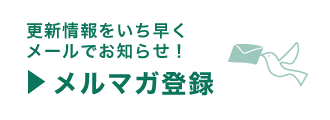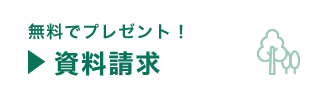がれきや葛のツタが絡まる荒廃地を開墾して米や野菜をつくる場合や家庭菜園やプランター栽培などにEM技術を取り入れるとしたら、どのようなステップを踏むのだろうか。EM技術とセットだとする整流結界をどのように施したら効果的なのか、そもそも栽培可能な土づくりのための効果的なEM技術や整流結界の導入はどこからどのように始めたらよいのだろうか。
これらに応える取り組みが三重県津市にあるミロクコミュニティ救世神教(以下:MC)が推進する「みろく菜園」で実施され、手ごたえを得たという報告が相次いでいます。
土づくりから収穫までを共に・・
みろく菜園は三重県下を中心に全国46カ所の拠点で田畑やプランターで米や野菜栽培に挑戦。農業初心者がEM技術の基本から始まり、土づくりから収穫までを仲間と共に学んでいます。ここでのキーワードは「自給自他足」です。自給自足は「自主独立」の意味合いですが、自給自他足には「生きることは食べること。自分の食べるものは自分でつくる。できた野菜を隣人や知人、ご近所へとお裾分けし、栽培技術も伝え、共に自立出来ることが立派な他足です」(MC:みろく菜園担当:山路誠二自然農法部部長)と言われるように利他愛の要素が含まれます。
このように、それぞれの菜園では自由な企画の下、徹底したEM技術の実習が行われていて収量や出来栄えに成果の証を見ることが出来るようになりました。
誰もがどんな条件下でも、挑戦して効果を実感できたというEM活用の現場の声と検証事例を連載でお届けします。
この<第1回>は取り組みの陣頭指揮を執っておられる山路誠二自然農法部部長のメッセージからスタートします。山路農法部長は令和6年11月30日に沖縄で開催されたユニバーサルビレッジ・EM国際会議で「EM塩除草の目指す、新たな稲作」と題してご自身が取り組んでいる米づくりについて発表しました。
<参考>
【DND 比嘉照夫氏の緊急提言 甦れ!食と健康と地球環境】
第211回 第2回正木一郎記念ユニバーサルビレッジ EM 国際会議(2)
【新・夢に生きる】第201回 第2回正木一郎記念ユニバーサルビレッジEM国際会議
【レポート】第2回 正木一郎記念 ユニバーサルビレッジ・EM国際会議
喜びを分かち合う菜園づくりに

山路部長:私は今、自然農法勉強会をさせていただいています。私は初めてEMで自然農法のお米をつくったとき、美味しくてね。嬉しくて皆さんに配っていました。「とても美味しかったよ」なんて聞くと舞い上がり、大いにやる気になりました。感動してもらうのは大事ですね。ある地域へ出向いた時に、「ダイコンの気持ちが分かってきたようです」と言う喜びの声を聞いて感動しました。やはり、愛情を込めることが、人にも野菜にも非常に大事ですね。私たちが感動や感謝をもって育てていくと喜びが生まれ、微生物が働いてくれる。そういうことを皆さんに分かってもらい、菜園づくりが広がっていくことを願っています。

小さな積み重ねからの仕組みづくりを
山路部長:それと、今、世界的な気候変動で食糧事情の先行きがどうなるか分からない時代なので、主食の米の確保のためにも「小さな田んぼでもよいから米づくりを始めてみましょう」と呼びかけているところです。さらに、もう一つ、海外から化学肥料の原料が入らなくなっている現状で、米ぬかなど有機肥料の争奪戦が目前に迫ってきています。しかし、EMと塩があれば良いお米が出来ることを実証すべく、目下私は自分の田圃で取り組んでいるところです。EMの開発者でおられる比嘉照夫琉球大学名誉教授が提唱されている、この「塩田んぼ」技術※1が世の中に出ていったら、素晴らしいです。これが広がれば広域環境浄化型自然農法※2が完成します。伊勢湾などをはじめ海の浄化にもつながります。そういうことを私たちが分かって、意識して活動をしたら、それは楽しい世界づくりになります。そういう仕組みづくりを皆さんと共にしていきたいです。
※1 <参考>本格的となってきたEMの原子転換力による塩の肥料化
※2 広域環境浄化型自然農法・・・自然界の微生物は発酵食品を生み出すなど有用な善玉菌が全体の1割、腐敗などをもたらす悪玉菌が1割、残りの8割はどちらでもない日和見菌だといわれています。EMにはこの自然界の日和見菌たちを善玉菌に呼び込む力があります。私たちがEMを使うことにより、自然界の善玉菌が増えて大きな力となり、環境の浄化、食物連鎖や生態系回復への助けとなります。私たち一人一人の行動は単なる農行(のうぎょう・微生物を活用した自然農法の実践)に留まらず、自然を、地球を救う力となります。
実施ほ場の紹介 <小川敦司さん方菜園(三重県四日市市)>
農行実践といわれても、どのように取り組めばよいのか分からない。まず作物を育てる場所がない。そう考える人は多いかもしれません。しかし、「悪条件は好条件」です。小川敦司さん(自然農法指導士・地球環境共生ネットワーク理事・執行委員)方の狭くて小さな畑。家の周囲に所狭しと並んだプランター。広く恵まれた環境だけが農行実践の全てではないことを教えてくれます。今回は小川さん方の手法のさわりを紹介し、今後基礎編、応用編に従って小川さんから詳細な解説をいただいていきます。